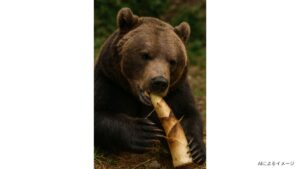はじめに
?「無煙炭化器を使えば煙が出ないから野焼きにはあたらない」?
?「木や竹を炭にするから大丈夫」?
?「農業用に使うなら規制の対象外」?
こうした言説を、ネット上で見聞きしたことがある方も多いと思います。
しかし実際に「法律上、本当に問題がないのか?」と不安に思われる方も少なくありません。
当社(株式会社STK商会)では、『無煙炭化器 匠』を製作・販売するにあたり、実際に大阪の弁護士事務所に相談を行いました。また消防署にも確認を重ねています。
ここでは、その経緯と専門家からの見解、そして弊社のスタンスをまとめてご紹介します。
関係法令の調査
まず関係しそうな法律は、主に以下の2点です。
A. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条の二 (焼却禁止)
B. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十四条 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
これらの法律は、「廃棄物の野焼きを原則禁止する」という趣旨で制定されているかと思います。
弁護士先生の見解
相談した弁護士の先生によると、以下のようなご指摘がありました(要約)。
- 施行令第十四条の例外規定に無煙炭化器の利用は該当しにくい。
- 竹が「廃棄物」と評価されるかどうかがポイント。
- 木くずが廃棄物とみなされるように、竹も「廃棄物」と見なされやすい。
- よって「廃棄物ではない」と主張するのは難しい。
つまり、ネット上で流布している「無煙炭化器だから野焼きではない」という言説を、そのまま鵜呑みにして販売するのは、法律的にリスクがあるという見解でした。
主に間伐した竹を竹炭にすることをテーマに質問させて頂きましたので、竹への回答ですが、間伐した木でも価値がない場合は同様と考えられます。
弊社のスタンス
この弁護士見解を踏まえ、当社は以下のような姿勢で販売を行っています。
- ネット上の断片的な情報を根拠にしない
- 法令遵守を前提に製品を案内
- 小売店様・ユーザー様にも正しい情報を共有
つまり、安心してご利用いただくためには「法令遵守」と「安全管理」を徹底することが大前提だと考えています。
安全に使うための共通認識
ユーザーの皆さまに共通認識として持っていただきたいのは次の3点です。
共通認識① 消防
各地域の消防署(消防本部)に届出を出しておきましょう。(連絡・相談)
この届出は、消防署がたき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは市民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるためです。 (ある消防署からのお知らせの引用)
各地域の消防署のホームページに書かれているように、届出を出しておかないと、野焼きの例外にあたらないと判断されるものと考えています。例外として扱って頂けると考えています。
廃棄物の処理の法・法令の意図も、無暗にゴミ(産業廃棄物含む)を焼却しないとの意図だと考えています。
余談ですが、公私で消防・救急の方に関わったことがありますが、皆さんすごく親身で良い方々です。
共通認識② 消火
『無煙炭化器 匠』 使い終わったら、消火する。山火事等を起こさないようにする。
ごくごく当たり前のことなのですがご注意をお願い致します。
共通認識③ 環境・法令に配慮する
廃棄物処理法の趣旨は「無暗にごみを焼却しないこと」と考えております。
農業・林業従事者やキャンプ利用など、法律上の例外も存在しますが、環境保全の視点を忘れず、責任を持って使用していただくことが大切だと思います。
各地域の市町村の環境課・環境係のホームページをみますと、たき火等は近隣の方への配慮がない場合は指導の対象になると書かれております。この点は、ユーザ様のご使用の環境によりますので、ユーザ様の環境に合わせた配慮をお願いいたします。
まとめ
環境に配慮し、コンプライアンスに反しない『無煙炭化器 匠』の使い方としては、
- ネットの言説をそのまま鵜吞みしない
- 各地域の消防署(消防本部)へ相談
- 使い終わったら消火をする
- 近隣の方への配慮
当社は、環境に配慮し、コンプライアンスを守った無煙炭化器の利用を推進しています。
竹枯れでお困りの場合は
間伐された竹材・不要となった竹材の有効活用方法として、『無煙炭化器 匠』により竹炭を製作することも可能です。楽天等でも販売されております。

※ [無煙炭化器 匠]の取説にも記載しておりますが、事前に各地域の消防署にご相談ください。