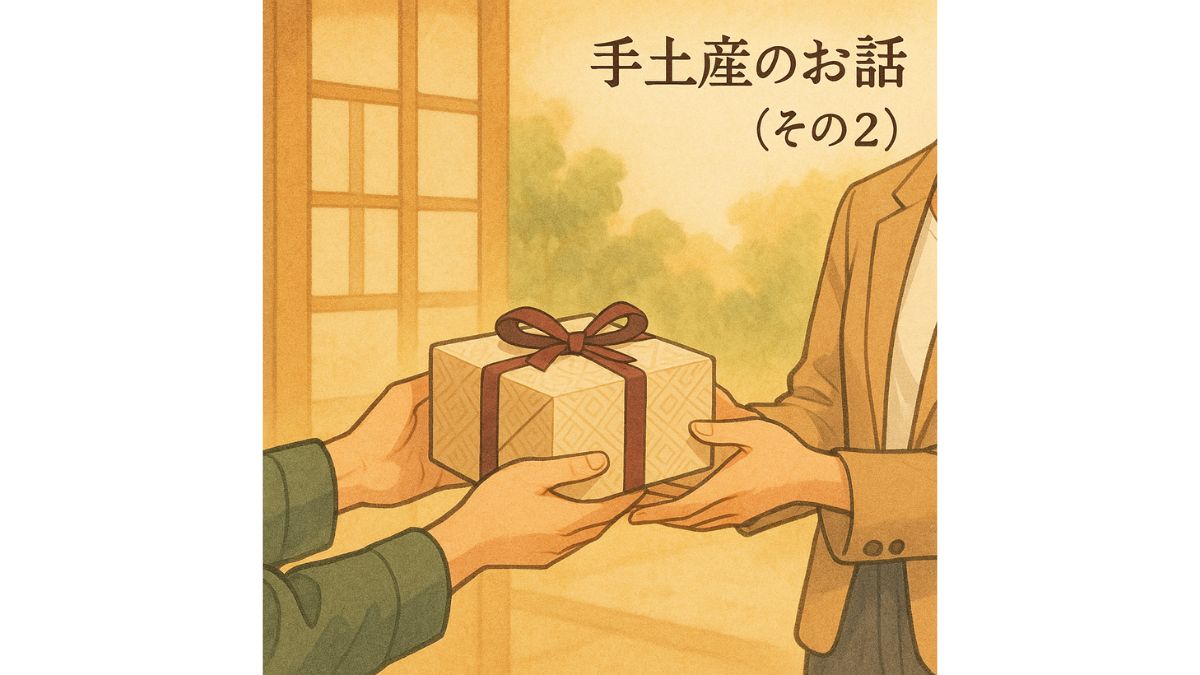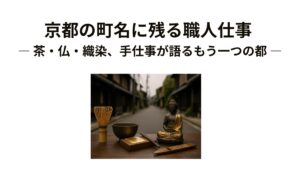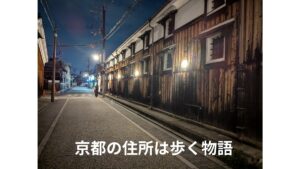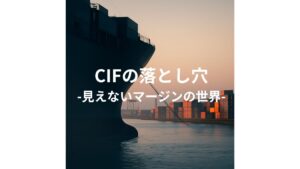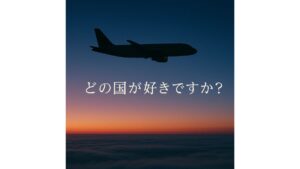前回、手土産についてさくっと触れましたが、今回は少し踏み込んで、筆者の場合どのように手土産を選んでいるかを、少しだけ京都という土地柄を背景にお話ししたいと思います。
手土産は「何を渡すか」より「どう選ぶか」
京都では昔から、贈り物は単なる“モノ”ではなく、“気持ちを表す媒介”として扱われてきました。
例えば和菓子ひとつにしても、桜の時期には桜餅、夏には涼やかな葛切りや水菓子、秋には栗や柿を使った菓子…と、季節を写し取ることが当たり前のように大切にされています。だからこそ手土産も、「高価なものかどうか」ではなく、「その時の場や相手との関係をどう映すか」で選ぶことが肝心だと思うのです。
相手の背景を意識する
社員の多い会社へ伺うなら、皆さんで分けやすい個包装の菓子。
少人数の事務所なら、質感のある一点ものでもいい。
相手が年上の方なら、老舗の落ち着いた品。
若い方が多いなら、少し洒落た遊び心のある品。
こうした“相手の背景”を想像して選ぶことで、形式的な手土産が「気が利くね」と言っていただける存在に変わります。
こちらの姿勢を映す
私は手土産に、自分の姿勢やメッセージを少し重ねるようにしています。
堅実さを伝えたいときは、定番の銘菓を。
フットワークの軽さを示したいときは、出張先や地元で見つけた品を。
また私ども在京都の企業では「実はこのお菓子、京都の○○で評判なんです」と一言添えるだけで、自分の背景も伝わり、会話の糸口にもなります。
私流のこだわり “ピリッと気の利いた一品”
さらに私流としては、ただ無難なものに落ち着かせるのではなく、場面に応じて「おや、そこまで考えているのか」と思わせる品を選ぶようにしています。
例えば、相手の好みや過去の会話をヒントにしたもの、季節感を一歩先取りしたもの、ちょっとユーモアを感じさせる小物など。
渡した瞬間に話題が生まれる、そんな“ピリッと効いた”手土産が、関係をぐっと近づけてくれると感じています。
選ぶうえで大切にしている「ストーリー」
そして私がもう一つ大事にしているのは、“手土産にストーリーを持たせること”です。
たとえば大手企業のトップを訪問したときのこと。こうしたステータスの方々は手土産をもらい慣れておられ、普通の内容では埋没してしまいます。そこで私は、その方ご自身ではなく秘書の方にターゲットを絞り、その年代の女性が喜ぶものを考えました。選んだのは、当時話題になって入手困難だった行列のできる人気商品。おそらくトップの方は秘書に渡し、皆さんで召し上がられるでしょう。その際、「わざわざ手に入りにくいものを持参した」というストーリーがフィードバックされ、結果的に好印象を持っていただけるのではないかと考えたのです。
また、海外訪問の際に日本の地酒を“一升瓶ごと”持参したこともあります。その国では入手できない品であり、しかも相手の出身地の銘柄を選び、スーツケースに割れないよう丁寧に梱包して運びました。無事に届けられたときの喜ばれ方は今も鮮明に覚えています。
このように、「ただの手土産」ではなく「どういう経緯で選んだか」「どんな思いを込めたか」というストーリーがあると、渡した瞬間以上の価値が生まれるのだと思います。
豪華さよりも心地よさを
手土産は豪華さで驚かせる必要はありません。
むしろ、相手が気を遣わずに受け取れる“控えめな心配り”の方が印象に残ります。
京都では「おおきに」と言って、さりげなく感謝を伝える文化がありますが、まさにそれと同じで、品物はあくまで脇役。
大切なのは「どうぞ皆さまで召し上がってください」「季節を感じていただければ幸いです」といった一言に込める心だと思います。
結びに
結局のところ、手土産は“渡すもの”ではなく、“相手を思う気持ちをどう形にするか”の表現です。
それは「豪華な品」ではなく「さりげない選び方」、そして時には“ピリッと気の利いた工夫”や“ちょっとしたストーリー”にこそ価値が宿るのだと感じます。
次に手土産を選ぶとき、ぜひ「なぜこの品を選んだのか」を一言で語れるかどうか。
そこを意識してみてはいかがでしょうか。