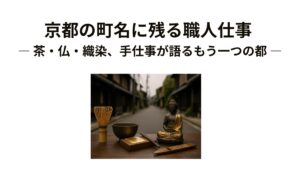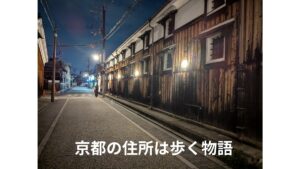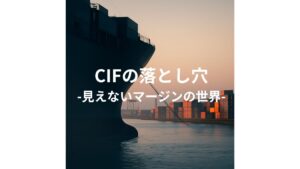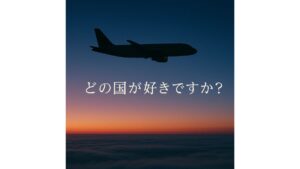無煙炭化器 使い方
今回は「無煙炭化器 匠」の使い方を、実際の写真付きでわかりやすく解説します。
初めての方でも「どのくらいの竹を入れるの?」「どこで火をつけるの?」などが一目で分かるように構成しています。
また、後半では良く疑問に思われる「法律面」「安全面」についても詳しく触れています。
無煙炭化器 匠の使い方は、通常の無煙炭化器の使い方と全く同じです。
1. 伐採した竹・木を無煙炭化器の大きさに合わせてカット
手持ちの無煙炭化器に合わせてカットします。セーバーソーがあると便利です。
この際カットに手をかけたくない場合は大きめの無煙炭化器を購入すると良いです。もしくはセット組(2個、3個)を用意しておくとかなり効率が上がります。
一方で、大きめの無煙炭化器は重いため、複数人での運搬など山の中へのもち運びが不便な場合があります。
場所・量に応じて、購入されると良いかと思います。

2. 無煙炭化器 匠を用意して、着火準備
無煙炭化器を用意して、その中に着火剤として乾燥させた竹・木の葉っぱ等を用意。
一部着火用に段ボール等を入れていますが、あくまで着火用としての分量です。(* このページの最後に解説)

コツ: 竹の葉、木の枝も着火剤として活用
3. 火がある程度着いたらカットした竹・木を投入!
着火して安定したら、竹・木を投入します。

コツ:複数個をセット購入していただけますと、こんな使い方も可能です。カットが面倒な方にはおすすめの使い方です!
4. 順次、投入
しばし、竹・木を順次放り込んでいきながら休息。 合わせて、消火用の水等も準備しておくと良いでしょう。
上手な炭化のコツ:一度に入れすぎると、少し煙が出やすくなります。

5. 消火
準備しておいた水で消火。今回は水で消火を行いました。 現在、消火用の蓋も開発中です。

お得な情報
弊社の「無煙炭化器 匠」は、他社製品と比較して価格が安く導入しやすい点が特徴です。個人の利用から地域活動まで幅広く対応できるサイズ展開・組数展開をご用意しています。大きい炭化器になりますと重くなり一人で持ち運びがしにくいのですが、持ち運びやすい炭化器を複数枚で同時に運用することでタイムパフォーマンス・コストパフォーマンス良く炭を生成できます。
「無煙炭化器 匠」シリーズ一覧の購入はこちらより

「法律面」「安全面」について
途中で但し書き等をしておりますが、こちらですが、『たき火』『野焼き』等の法令と関係しております。
ご存知の方は、読み飛ばしてください。
農業・林業を営まれておられる方はご存知かもしれませんが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で農業・林業の場合『野焼き』が例外として認められております。また一般の方も『たき火』等は例外として、認められておりますが、火災等と紛らわしい場合・みだりに廃棄物を焼却する行為等は罰せられる可能性もあります。
無煙炭化器と野焼き・たき火の法的関係はこちらから。

要点は、近隣に灰・火の粉(火災)・匂いで迷惑をかけない、火災と間違われない、一般ゴミをみだりに焼却しない。また消防へ相談しておくと言った点です。
良くある質問
地域の竹枯れ活用事例


竹を炭化して再利用することは、国としても推進されています。